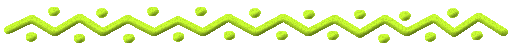
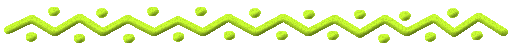
伊東静雄について
富士 正晴 伊東静雄の詩はすべて哀歌だと私は考える。
そして彼の生活そのものが哀歌であろう。哀歌を歌う人は確乎としていなければならぬ。哀歌は悲劇であり、そして心を打つ悲劇は強い人間によってのみ、描かれて力を持つのだ。 心の美しい人が、その心の美しさのために苦しまねばならず、しかも確乎として生きるとき、哀歌は生まれ、生きる。 伊東静雄の生活の中には運命というようなものがあるように私には思われる。運命いう言葉を書く必要は彼にない。(何故なら、彼の生活そのものが運命の受容であり、運命の諦視ということの自覚生活なのだろうから。彼は自覚して、運命を受容するのだ)如何なる方面、如何なる意味を持つ生活にせよ、その自覚的な生活こそ詩人の持たねばならぬ生活であろう。そして詩人とえせ詩人との間の超えることのできない差異を、決定的に生ずる一点こそここにある。 伊東静雄の詩のあの陶器の面に見られるような硬度の冷たさは、この自覚的生活の冷たさだ。彼が自覚する時、彼は冷たい世界にすむ。彼の心は常に自覚に、とぎすまされ、その磨かれ方が冷たいのだ。 彼の詩のリトムの一種ののろさは彼の生活に彼が力をこめて加える統制力からくる。彼の生命は静かであり、強い。しかもそれは憂鬱の強さに外ならないのだ。 年若いままに老いを掴み、その老いの中より現在を自覚する時、それは非常に冷静な美しい憂鬱、人が皆酔っているとき一人醒めて居り、その酔いを見つめ、又同時に一人醒めている自己の姿を忘れることのないその澄み切った目を持っているのだ。 (中略) 彼は一つの動きを分解し、逆もどりし、先行し、組み直して見る。彼は詩に於いて一種の立体派の仕事をやっているとさえ言えるのだ。これは併し、彼の性格の構造であろうし、彼は彼の性格のままに世界をくみ直す自己を冷静に肯定するであろう。 1971年刊 富士正晴編 「伊東静雄研究」より |